幕張は“暮らせない未来都市”だったのか?──生活感と違和感が同居する街を歩く
投稿日:2025年7月
目次
JR海浜幕張駅|街の玄関に“異常に広い余白”
JR海浜幕張駅の北口を出ると、まず圧倒されるのが“広すぎる駅前空間”。このロータリーと通路は、イベント動員や大量輸送を見越した設計だと思われますが、日常的にはやや不自然な静けさが漂います。
ベイタウンの高層住宅と生活インフラ
「未来都市=人がいない」という印象とは裏腹に、幕張ベイタウンにはしっかりとした生活のインフラが整備されています。大型マンション群と地域バスがその暮らしを支えており、駅前の静けさとは対照的な“生活の息吹”が感じられます。
緑道と小学校|想像以上の“暮らし”があった
現地を歩いていて驚かされるのが、しっかりとした生活導線。小学校もあり、子どもたちの笑い声が響いています。都市設計の美しさの中に、確かに“人間の暮らし”が存在しているのです。
遊泳禁止の海|管理された都市空間の象徴
「海が近いなら泳ぎたい」と思うのは自然な発想。しかし、幕張の浜辺には柵が設置され、「海水浴場を開設していません」「遊泳・水浴はできません」という看板が掲示されています。この街では、海でさえも用途が厳しく限定されているのです。
都市設計の謎|誰のための街なのか?
幕張新都心の案内図を見ると、イベントホール、ホテル、大学、企業施設が効率的に配置されており、まるで“ショーケース都市”のよう。住民のためというより、来訪者のための機能性が優先されていることが見てとれます。
まとめ|“住めるけど、住みにくい”未来都市
幕張には確かに人が暮らしている。だが、“都市としての優先順位”はどこかズレている。効率、整備、管理……未来的であるがゆえに、生活のゆらぎが許されない。幕張は、非日常と日常の狭間で揺れる“実験都市”なのかもしれません。
▼ 現地取材に便利だったおすすめアイテム
※当サイトはAmazonアソシエイトとして適格販売により収益を得ています。
次回予告:「イオンモールが支配する都市──幕張新都心の“モール依存構造”の真実」に迫ります。
▼YouTubeでも現地映像を公開中
▶ ジモトのナゾ旅チャンネルはこちら

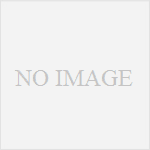
コメント