長野県・諏訪湖の周囲に、同じ名前を持つ神社が4つ存在します。
その名は「諏訪大社」。
本宮、前宮、春宮、秋宮。
どれも諏訪大社と呼ばれ、全国の神社の中でも極めて異例な構造です。
なぜ、一つの神社が“4つ”にも分かれて存在するのか。
その理由を探ると、地形、神話、そして分断された歴史が見えてきました。
■ 諏訪大社はなぜ4つに分かれているのか?
まず基本から整理すると、諏訪大社は以下のように分かれています。
名称 所在地 特徴
本宮 茅野市 最も古く、神体山・守屋山を祀る
前宮 茅野市 本宮の補助的役割。建御名方神が降り立った地とされる
春宮 下諏訪町 下社の冬の祭祀が行われる
秋宮 下諏訪町 下社の夏の祭祀が行われる
これらは「上社(本宮・前宮)」と「下社(春宮・秋宮)」に分かれ、
物理的にも10km以上離れた場所にあります。
これは単なる“分社”ではありません。
それぞれが独立した歴史と信仰を持ちつつも、諏訪大社として統合されているという、全国的にも類を見ない構造です。
■ “4社構造”を生んだのは、地形と民族の分断
諏訪盆地は、南北に長く、山に囲まれた閉鎖的地形。
上社がある茅野市は山間部、下社のある下諏訪町は宿場町として発展しました。
この地理的な隔たりは、もともと異なる民族や豪族の影響下にあったことを示唆します。
実際に、上社と下社では祭神の性質や儀式のスタイルも微妙に異なり、
時代によっては権力闘争さえあったといわれます。
この「分断と共存」が、結果として“4つの社”という形に落ち着いたのです。
■ 建御名方神──「国譲りを拒んだ神」の謎
諏訪大社の主祭神は、建御名方神(たけみなかたのかみ)。
日本神話において、建御名方神は「国譲り」を迫られた大国主命の子であり、
ヤマト政権の使者に最後まで抵抗した“敗者の神”です。
敗北した建御名方神は、出雲を追われ、諏訪に逃れたと伝えられます。
そのため諏訪大社は、「征服された神を祀る、異端の神社」ともいわれてきました。
■ 御柱祭──命がけの神事は、地霊との契約だった?
諏訪大社を語る上で外せないのが、「御柱祭(おんばしらさい)」。
7年に一度、直径1m以上の巨大な丸太(御柱)を山から引きずり下ろし、
各社の四隅に建てるこの祭りは、命がけの祭礼としても知られます。
特に有名なのが「木落とし坂」。
丸太とともに坂を滑り落ちる光景は勇壮である一方、過去には死亡事故も発生しています。
この祭り、実は「神を鎮め、土地の霊を封じる儀式」として行われていたという説も。
つまり御柱祭とは、諏訪の土地そのものと“契約”を結び直す神事だったのです。
■ 地図に見る“諏訪の分断”構造
地図を俯瞰して見ると、
上社(茅野市)は“山の民”のエリア、
下社(下諏訪町)は“街道の民”のエリアに対応していることが分かります。
そして諏訪湖を挟むこの構造は、まるで「古代国家の内戦ライン」のよう。
この視点で見ると、諏訪大社の4社構造は「和平の象徴」とすら読み取れます。
■ あなたも“分断された神社”を歩いてみませんか?
実際に現地を歩いてみると、
4社それぞれに「空気感」がまったく違うことに驚かされます。
神聖、静寂、荒々しさ、華やかさ。
それぞれの社には、それぞれの物語があります。
私は今回、すべての社を徒歩と車で巡りながら撮影しました。
その中で宿泊した旅館「◯◯(実際の宿名)」がとても印象的だったので、
ぜひ諏訪を訪れる方にオススメしたいと思います。
→【じゃらんで「◯◯」の空室状況を見る】
→【楽天トラベルで諏訪の宿を探す】
■ おすすめ書籍(知識を深掘りしたい方へ)
『諏訪信仰と御柱祭』 →【Amazonで見る】
『古代出雲と建御名方神の真実』 →【楽天ブックスで見る】
■ 撮影機材・旅の便利グッズ(現地で使いました)
【Amazon】神社巡りに最適な軽量三脚 → [リンク]
【楽天】トレッキングにも使える防水スニーカー → [リンク]
【Amazon】大容量モバイルバッテリー(御柱祭用に超便利)→ [リンク]
■ 次回予告
次回は、「御柱祭に命をかける理由」
地元の人々に直接聞いた、“諏訪の男たちが丸太を引く本当の意味”に迫ります。
→ 【YouTubeチャンネル:ジモトのナゾ旅】
→ 【チャンネル登録はこちら】

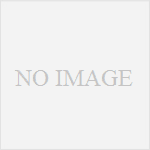
コメント